![]()
| ア | |
| 1五行 | 木 |
| 2五季 | 春 |
| 3五臓 | 肝 |
| 4五腑 | 胆 |
| 5五官 | 目 |
| 6五主 | 筋 |
| 7五志 | 怒 |
| 8五声 | 呼 |
| 9五気 | 風 |
| 10五色 | 青 |
| 11五味 | 酸 |
| 12五指 | 薬指 |
| 13陰経 | 厥陰・足 |
| 14陽経 | 少陽・足 |
| 15五神 | 魂 |
| 16五液 | 涙 |
| 17五支 | 爪 |
| 18五変 | 握・攣 |
| 19五方 | 東 |
| 20五役 | 色 |
| 21五不足 | 恐 |
| 22五時間 | 平旦 |
| 23五目部 | 黒精 |
| 24五時 | 朝 |
| 25五労 | 久行 |
こちらの五行色体表について、この証について(アの縦列)を抜粋すると、上のようになります。
こちらにカテゴライズされるものを
(東洋医学)肝虚≠肝臓トラブル(西洋医学)
肝の臓は足の厥陰肝経(あしのけついんかんけい)というエネルギーが走行するルートと一体になって、生命状態に関わっています。
以下のような症状について、すべてが当てはまることはありませんが、肝虚証になると1つ以上の項目にあてはまることになります。
(この証になりやすい人の特徴)
1 この証になりやすい人の性格・メンタル的に特徴
2 この証になりやすい人の肉体的特徴や体質、身体的弱点など
3 発症しやすい症状(ここではエネルギーのルート上に問題が生じている場合を例に挙げました)
(養生法)
セルフケアにより可動域を広げる方法
自分の身体に灸をする場合
鍼灸施術によるアプローチ
(症状や特徴)
1この証になりやすい人の性格・メンタル的な特徴
(ア)強いストレスが原因で体調不良に陥りやすい。
肝という臓腑は、おおらかに上へ上へと伸びたがる性質があります。それを押さえつけられることにより、気が滞り発症しやすいです。

(イ)怒りやすい
気が滞った場合の症状です。五行色体表(7五志)は怒です。

(ウ)情緒変動に大きく左右されやすい
肝は情緒を

(エ)気が短くせっかち
肝の志は怒です。イライラ・ヒステリーなど。
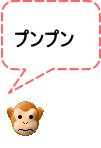
(オ)神経質で繊細
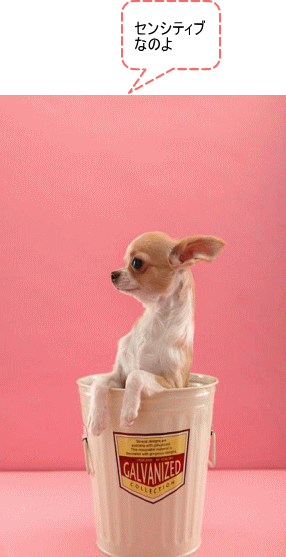
(カ)自分の意見をハッキリと主張するが、後で後悔しがち。
ハッキリと自分の意見をいえることもありますが、後で後悔することが多いようです。反対に言いたいことがいえない場合もあり、その差が激しいのが特徴です。
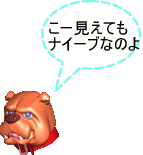
(キ)神経が高ぶって、不眠になりやすい
ピリピリして穏やかな気持ちになれない時があります。夜寝ようと思っても、昼間の出来事が気になって眠れないことがある傾向があります。
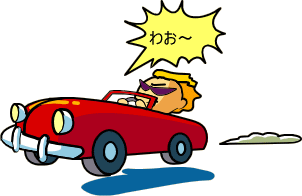
(ク)早口でしゃべる特徴がある。
気性が異常亢進することがあり(波がある)、頭の回転も速いため、早口でしゃべる傾向があります。よって、相手に聞き返されることがあります。
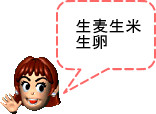
(ケ)人が話し終わるのを待たずに自分が話したい傾向がある
テンポが速いため、人が話し終わるのを待たずに自分の話をしたがる傾向があります。ストレスが少ないときはユッタリとしていられますが、多忙な仕事などでストレスがたまるほど、こうした傾向が強くなります。

(コ)曲がったことが許せないことが多い
「肝胆相照らす仲」といいますが、肝が不安定になると胆にも悪影響が及びます(3五臓 4五腑)。胆には正義心が宿るため、他人の曲がった行為が許せなくなります(胆の異常亢進)。そのこと自体は悪いことではありませんが、あまりこだわりすぎても体調を崩す傾向があります。

ページの最初に戻る
2 この証になりやすい人の肉体的特徴や体質、身体的弱点など
(ア)消化器に影響が出やすい
五行論において、肝は脾(消化器)を剋します。肝→脾の
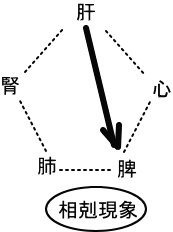
(イ)ストレスで吐き気をもよおしやすい(機能性ディスペプシアなど)
上と同じ意味です。

(ウ)眼症状になりやすい(眼精疲労・目のかすみ等)。
目は肝の
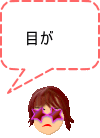
(エ)口が苦いくなりやすい
肝・胆が関わっています。
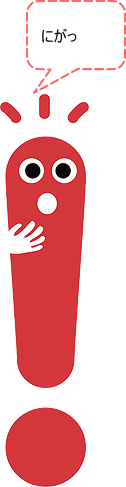
(オ)胸が
肝の症状は、胸や脇腹に症状が出やすい傾向があります。
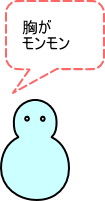
(カ)
胸や脇腹が張って違和感があることをいいます。

(キ)舌の両脇だけが、ほかの部分と違うことが散見される
肝の状態は舌の両脇に表れます。肝が異常亢進すると、この部分の赤が鮮明になるなど、ほかの部分と違って見えます。

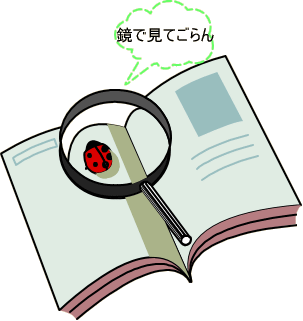
ページの最初に戻る
3 発症しやすい症状ここでは特に、エネルギーのルート上に問題がある場合を挙げています。
(ア)側頭部や頭頂部の頭痛
側頭部頭痛は
足の厥陰肝経(あしのけついんかんけい)は頭頂部を通り、足の少陽胆経(あしのしょうようたんけい)は側頭部を通るからです。
肝と胆は表裏の関係にあります。

(イ)腰痛・座骨神経痛など…体を横に倒すと痛みが顕著
(参考)
体の横側を伸ばすと症状が悪化します。胆は体の横(特に腰から下肢にかけての外側)を

(痛む部位は腰・大腿・下腿などケースバイケース)
※どこが痛いかではなく、どういう体勢で痛いかに焦点を当てて考えるのが東洋医学です。
(ウ)腰痛・座骨神経痛など…体をひねると悪化が顕著
(参考)
上の(イ)と同様に、体の横を伸ばす動作だからです。腰・股関節・膝・下肢など、どの部位に痛みが出るかはケースバイケースです。胆は体の横(特に腰から下肢にかけての外側)を

(痛む部位は腰・大腿・下腿などケースバイケース)
※どこが痛いかではなく、どういう体勢で痛いかに焦点を当てて考えるのが東洋医学です。
(エ)膝痛など…脚を組むと悪化が顕著
(参考)
下肢の外側を伸ばすと痛みが出ます。胆は腰〜下肢の外側(横)を

(痛む部位は腰・大腿・下腿などケースバイケース)
※どこが痛いかではなく、どういう体勢で痛いかに焦点を当てて考えるのが東洋医学です。
(オ)足首痛…外くるぶし側を伸ばすと悪化が顕著
(参考)
足首の外側を伸ばすと痛みが出ます。胆は下肢の外側(横)を

(痛む部位は腰・大腿・下腿などケースバイケース)
※どこが痛いかではなく、どういう体勢で痛いかに焦点を当てて考えるのが東洋医学です。
(カ)膝痛…あぐらをかくと悪化が顕著
(参考)
下肢の内側を伸ばすと痛みが出ます。腰・股関節・膝・下肢など、どの部位に出るかはケースバイケースです。肝は下肢の内側(横)を
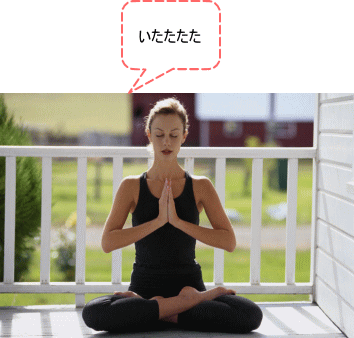
(痛む部位は腰・大腿・下腿などケースバイケース)
※どこが痛いかではなく、どういう体勢で痛いかに焦点を当てて考えるのが東洋医学です。
(キ)腰痛・座骨神経痛など…脚を開くと悪化が顕著
(参考)
上の(カ)と同様に、下肢の内側を伸ばす動作だからです。腰・股関節・膝・下肢など、どの部位に痛みが出るかはケースバイケースです。肝は下肢の内側(横)を

(痛む部位は腰・大腿・下腿などケースバイケース)
※どこが痛いかではなく、どういう体勢で痛いかに焦点を当てて考えるのが東洋医学です。
ページの最初に戻る
(養生法)
(ア)全てに共通する養生法を実践する。
こちらをごらんくだい。
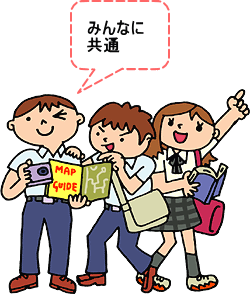
(イ)酸っぱいものを適度に飲食する。
酸味を適度に摂取すると、肝を活性化します(11五味)。摂りすぎると悪影響ですので、注意しましょう。
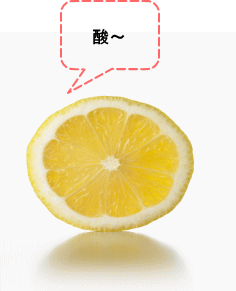
(ウ)朝食は軽めに。
朝は肝が旺盛に働きます(24五時)。その時間帯にたくさん食べて胃腸に負担をかけると、肝が旺盛に働きません。肝を旺盛に働かせるためには、少なめが良いでしょう。
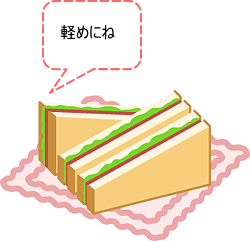
(エ)目は使いすぎない。
目を使いすぎることにより、肝に負担がかかります(5五官は目)。休憩をとりながら行いましょう。
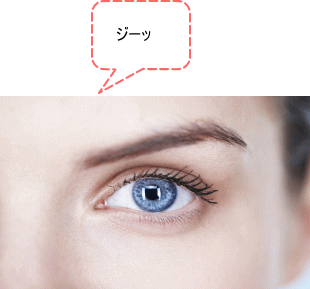
(オ)朝は早めに起きる。
朝の東からの大気を吸うと、肝が活性化します(19五方)。遅寝も睡眠不足も、あまり良くありません。

(カ)肝に効く飲食物を摂る。
小豆、黒豆、ナス、クコの実、キクラゲ、カボチャ、小松菜、ごま、

(キ)インスタント食品を控える。
添加物などは神経の状態に悪影響が及ぶことがあります。神経は肝が
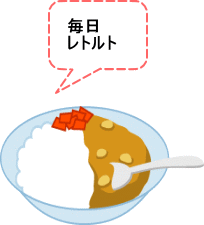
(ク)辛い食品を控える。
辛い味は肺を亢進させますが(11五味)、肺が亢進すると肝を攻撃します。これを

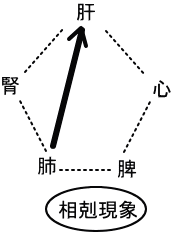
(ケ)果物類の常食をやめる。
果物類は適度に摂ると効果的です。しかし、いつも摂取していると、酸味や糖分をとり過ぎる可能性があります。

(コ)運動のしすぎに気をつける。
筋を
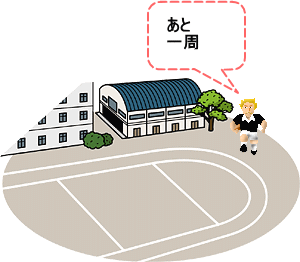
(サ)長時間にわたって風に当たらない。
皮膚に風が当たると知覚神経を刺激しすぎるため、肝に悪影響です(9五気)。

(シ)身体を締め付ける衣類などは控える。
肝はおおらかに、外がわに伸び伸びとしていたい臓腑です。それはメンタルだけでなく、肉体的にも同様です。また、締め付けることにより、筋肉運動を妨げることになります(筋は肝がつかさどる)。

ページの最初に戻る
セルフケアにより可動域を広げる方法
3エネルギーのルート上に異変が生じて、特定の体勢になる動きをすると痛みなどのため、可動域が制限される場合(イ) (ウ) (エ) (オ) (カ) (キ)、 セルフケアにより可動域を広げられる可能性があります。
このページの症状の場合、足の厥陰肝経(あしのけついんかんけい)または足の少陽胆経(あしのしょうようたんけい)に対して、アプローチを図ることになります。
自分の身体に灸をする場合
セルフ灸についてをご覧ください。
どんなツボが候補に挙がるか?
一例として足の厥陰肝経に関連するツボ「太衝(たいしょう)」 、足の少陽胆経に関連するツボ「丘墟(きゅうきょ)」が候補になります。

このページの最初へ
鍼灸施術によるアプローチ
(1)肝・胆のエネルギーが不足していることにより、エネルギーをスムーズに流せないことが原因で


今現在の症状に見舞われている(その人の弱い所に症状が出現)※個々人によって出てくる症状や部位は千差万別
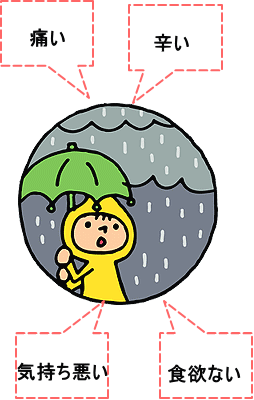

(2)ツボを通して肝の臓、胆の腑に刺激を与える
ツボ
↓
肝の臓、胆の腑
↓
他の臓腑(五臓六腑)
ツボとは、経絡(エネルギーのルート)を通して五臓六腑に通じるアプローチ・ポイント(正式名称は
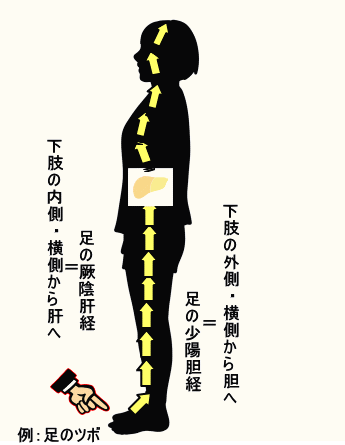
(甲)足の厥陰肝経(あしのけついんかんけい)
=ツボを通して肝の臓へ通じるエネルギーの通り道(=経脈)読み:けいみゃく
(乙)足の少陽胆経(あしのしょうようたんけい)
=ツボを通して胆の腑へ通じるエネルギーの通り道(=経脈)
〇経脈(甲)と経脈(乙)を横に繋ぐルート=絡脈(らくみゃく)
〇経脈+絡脈=経絡(けいらく)

※施術が奏功すれば・・・
(3)肝・胆が活性化して、閉じ込められていたエネルギーを解放する。
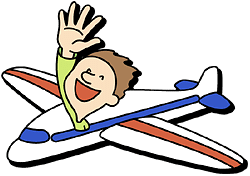

(4)五臓六腑全体が活性化して、滞っていたエネルギーを体の隅々まで流す
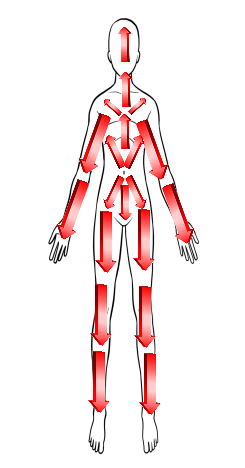

(5)自然治癒力が向上し、当該症状(または部位)を修復する

ページの最初に戻る
トップページへ
Copyright(C)2005-2026 Nagashima Acupuncture Moxibustion Room(Tsutomu Nagashima)長嶋鍼灸室